御旅所祭について
Otabisyosai
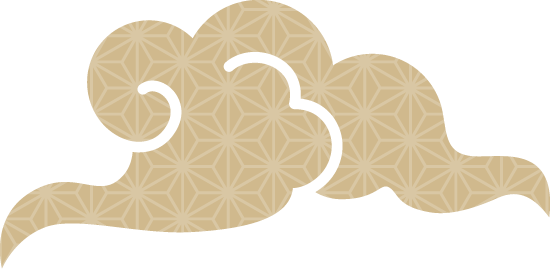
御旅所祭は午後2時半に始まる。御渡り式最後の大名行列のかけ声が、まだ参道にこだましているなかを神職が参進し、左・右の鼉太鼓が鼕々と打ち鳴らされ、奏楽(十天楽)のうちに若宮様にお供え(神饌)が捧げられる。このお供えは、お米を青黄赤白に染め分けて飾る「染御供」など古式の珍しいものである。
奉納(文化財指定古典芸能)
午後3時半〜午後10時半頃まで
神楽(かぐら)

東遊(あずまあそび)

田楽(でんがく)

細男(せいのお)

神功皇后の故事にちなむもので、筑紫の浜で、ある老人が「細男を舞えば磯良と申す者が海中より出て干珠、満珠の玉を献上す」と言ったので、これを舞ったところ、磯良が出てきたが顔に貝殻がついていたので覆面をしていたという物語りが伝わっており、八幡神系の芸能と考えられている。
神楽式(かぐらしき)

神楽式とは、翁を略式にしたものである。翁は新年や大事な演能会・神事の能のはじめには必ず行われて、天下泰平・国土安穏を祈願する儀式である。
常の翁はすべてが仰々しいものであるが、この神楽式は、シテの翁は浄衣に白の指貫をつけ、三番三は浄衣に白の大口をつけ、面はつけずに舞う。千歳は出ない。地謡や囃子方は裃を着用する。
後見が最初に正先へ鈴を出し、囃子方と地謡が座に着いてから、シテの翁と三番三が出て、翁が始まる。三番三は翁返りのあとすぐ鈴の段を舞う。
明治の初年、金春広成が、金剛氏成と協議の上定められ、おん祭の御旅所神前の特別な翁として現在に至っている。
和舞(やまとまい)

和舞は大和の風俗舞で、春日大社では古くから行われてきた。現在、神主舞が四曲、諸司舞六曲及び進歌・立歌・槲酒歌・交替歌・神主舞前歌等が伝えられている。
神主舞は一人または二人で、諸司舞は四人または六人にて舞われる。舞人は巻纓の冠に採物として榊の枝や桧扇をもち、青摺の小忌衣をつけ虎皮の尻鞘で飾られた太刀を佩く。諸司舞の四段以降は小忌衣の右袖をぬぐ。歌方は、和琴・笏拍子(歌)・神楽笛・篳篥及び付歌・琴持にて行われる。
おん祭では神主舞一曲、諸司舞二曲が舞われるのが近年の通例となっている。
舞楽(その1)
舞楽は、飛鳥・白鳳から奈良時代にかけて古代朝鮮や中国大陸から伝えられ、わが国において大成されたもので、のちに日本で作られたものも含めて、その伝来や特徴から左舞及び右舞に分類されている。

振鉾三節(えんぶさんせつ)

萬歳楽(まんざいらく)=左舞

延喜楽(えんぎらく)=右舞

賀殿(かてん)=左舞

地久(ちきゅう)=右舞
朝鮮半島伝来の四人舞で、緑色常装束に赤い優しい面をつけ、鳳凰をあしらった鳥甲を冠って舞う優美な舞で破と急がある。
曲名の「地久」は、大地が永久に変わらず、存在するのを意味しているといわれている。

長保楽(ちょうぼうらく)=右舞
保曽呂久世利を破の曲に賀利夜須を急の曲として一条天皇の長保年間(999~1004)に一曲にまとめたもので、その時の年号を曲名にしたといわれている。地久と同じく四人舞で、蛮絵装束に巻纓冠を着して舞う。
以上の萬歳楽から長保楽までの曲を平舞という。
舞楽(その2)

蘭陵王(らんりょうおう)=左舞
長恭は美青年だったため戦場におもむく時は、いつも恐ろしい面をつけて軍を指揮し、その武勇は轟いていたという。
舞人は竜頭を頭上にし、あごをひもで吊り下げて金色の面をつけ、緋房のついた金色の桴をもち、朱の袍に雲竜を表した裲襠装束をつけて勇壮に舞う。舞楽の中でも最も代表的なもののひとつである。

納曽利(なそり)=右舞
蘭陵王とともに一対をなし、競馬の「勝負舞」とされている。御渡り式の折、表参道で行われた勝敗によって、勝者が先に敗者があとに奉納される。

散手(さんじゅ)=左舞
これは神功皇后の時に率川明神が先頭にたって軍士を指揮した様を表したものといわれている。
舞人は赤い隆鼻黒髭の威厳のある面をつけ、別様の鳥甲をかぶり、毛べりの裲襠装束を着け、太刀を佩き、鉾をもって舞う。
その舞い振りは勇壮活発で、武将らしい荘重な感じが漂っている。一人舞で、序と破が伝わっている。

貴徳(きとく)=右舞
破と急が伝わっている。散手と番舞で「中門遷の舞楽」といい、かつて興福寺一乗院宮、大乗院御門跡、春日社司らがこの間に出仕したという。

抜頭(ばとう)=左舞
猛獣を退治した孝子の物語を表わしたもので、太鼓と笛の部分は獣と格闘する場面、合奏の時は復仇を了え、山路を両手でわけつつ、喜踊して降ってくる状を表す。

落蹲(らくそん)=右舞
以上の三番(六曲)を走舞という。